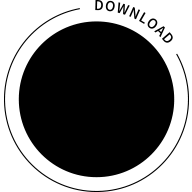envisionの種
2025/12/25
風呂式 「なぜ銭湯か?- まちと人がゆるくつながる方法 – 」Vol.1(3回連載)
コラム
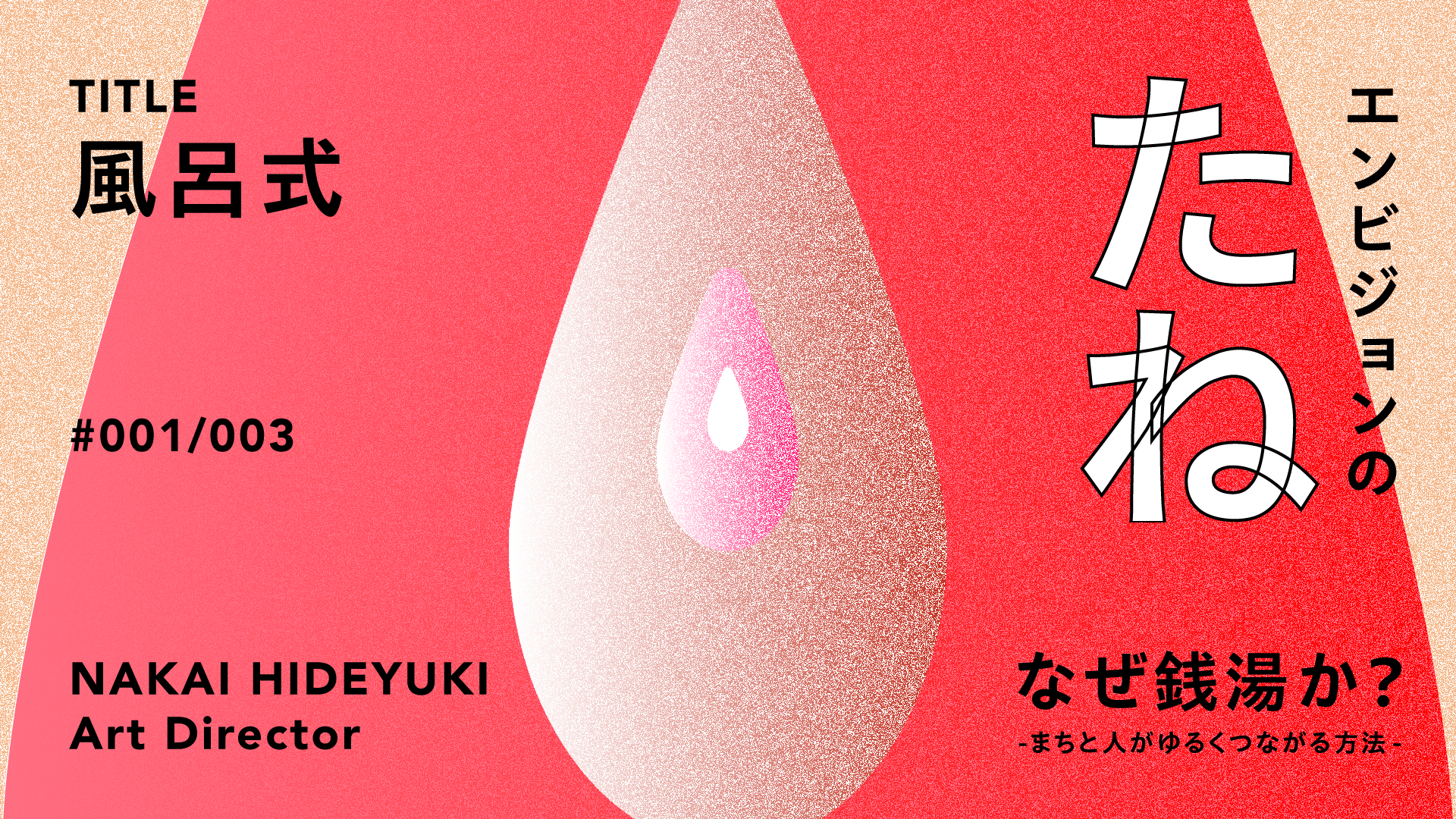
この連載は、銭湯を手がかりに、人と人、そしてまちとの関係を、いちアートディレクターの視点から考えるものです。銭湯が好きでよく通っていますが、自分の住むまちでは、体感でも分かるほどの勢いで、その数が減り続けています。効率や正しさ、意味のあるつながりが求められる社会の中で、銭湯には、そうした価値観から少し距離を置いた時間が流れています。何かを成し遂げなくてもよく、誰かと深く関わらなくてもいい。ただ湯に浸かり、調子を整えて帰っていく。その「ゆるさ」に、惹かれています。誰でも行けて、誰でも受け入れてくれる。強いコミュニケーションではなく、同じ湯船に浸かることで生まれる、脆弱な連帯感。「みんな」ではないけれど、「ひとり」でもない。
そんな銭湯のあり方を起点に、カルチャーやデザイン、クリエイティブの思考を広げながら、人やまちにとって必要な「ゆるさ」や「余白」について考えていきます。銭湯の継承に、微力ながらも一助になれたらと思い、書きました。

中井英之
Art Director
これまでメンズインナーやライフスタイルブランドのクリエイティブディレクションを経験。クライアントとユーザーの間で誠実なコミュニケーションを築く事がモットー。インパクトのあるビジュアルづくりが得意だが、アウトプットにとらわれず、常にオルタナティブな選択肢を探っている。
煙突を見つけたとき
列車で住宅街を通り抜けると、屋根の波のあいだから一本の煙突が見えた。湯気が薄く立ちのぼっている。銭湯だと思うだけで、見知らぬ街にも生活の温度があるような気がして安心する。お湯を焚く場所があるということは、そこに人がいて、暮らしがあり、まちがまだ呼吸しているということだ。
銭湯の煙突は、生活のディテールのなかに潜むまちの象徴でもある。効率や利便性では測れない、人の営みの“リズム”を可視化している。まちはこのような細部に支えられているのだと思う。
まちの余白
デザインにおいて「ネガティブスペース」は、何も描かれていない余白を指す。けれど、その余白があることで全体のリズムや意味が成立する。まちも同じだ。道路やビルが構造を形づくっているように見えて、実際にはその“あいだ”にある空間こそが、まちを呼吸させている。
銭湯は、その“あいだ”に生まれた場所である。働く場でも、消費の場でもない。目的を問わず人が集まることで、まちのリズムが整えられる。銭湯は、建築的な構造以上に、まちの呼吸を維持するための余白として機能している。
同じ温度を共有すること
家庭に風呂がある時代に、なぜ人は銭湯へ行くのか。そこには、個人の時間と他者の時間がゆるやかに重なり合う感覚がある。会話を交わさずとも、同じ湯の温度に身を委ねるだけで、何かが同期する。
私自身も大学進学でひとり暮らしを始めたとき、住んだアパートに風呂がなく、否応なく銭湯へ通う日々を送った。湯に浸かることが習慣になり、銭湯は日常のなかに組み込まれた。熱いお湯のあとに冷たい水風呂に頭から潜ると(本当はやってはいけないのだけれど)、一瞬だけ音が消え、湯や人の気配が遠のく。その無音の時間が心地よく、世界から自分が少しだけ離れていくように感じた。
強い関係をつくるのではなく、ただ同じ空間に存在しているという事実が、まちのなかでの自分の輪郭を確かめる行為になっている。銭湯の構造は単純だが、社会的には豊かである。年齢や職業、立場の異なる人が同じ空間で過ごし、同じ条件のもとで時間を共有する。その中で、境界は一時的に曖昧になる。そうした匿名性のなかにこそ、まちが人の場所であり続けるための仕組みがある。
まちの呼吸としての銭湯
昼の銭湯に入ると、天井の高い空間に光が落ち、湯の音が一定のリズムで響いている。人々の静かな動作がまち全体の呼吸と重なるように感じる。銭湯とは、まちが自分の体温を確かめるための場所であり、社会がまだ“人の時間”を持っていることを思い出させる装置だ。
銭湯はまちの余白として存在しながら、人と人、人とまちをゆるやかに結び直している。これからまちがどんな形に変わっても、その余白が失われない限り、まちはまだ人の暮らしに寄り添うことができるだろう。この連載では、そんな銭湯がこれからもまちの“日常”として持続できる方法を模索していきたい。効率や流行ではなく、人がまちと関係を結び直すための小さな仕組みとして、銭湯をもう一度見つめ直していくつもりだ。