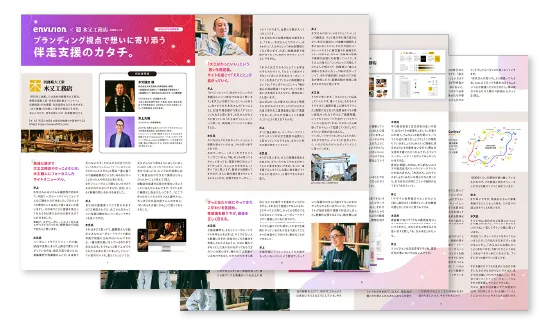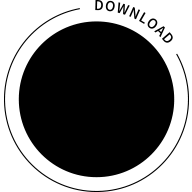INSIGHTS
2025/10/16
競わずして愛される、オンリーワンな「モテるお酢屋」の経営哲学。【中篇】
対談記事

3代にわたってさまざまなステークホルダーとの絆を丁寧に築き、5代目にして「モテるお酢屋」を経営理念に掲げるまでになった飯尾醸造。これまでの歩みについて伺った前篇に続き、中篇は未来ビジョンについてお聞きします。美食を軸にしたまちづくりや、他地域との連携など、お酢屋の垣根を超えて活躍するその行動力の源泉はどこにあるのでしょうか。

飯尾彰浩 様
株式会社飯尾醸造 5代目当主
日本コカ・コーラ社で提案型営業のプログラム開発と実践教育にたずさわったのち、2004年に家業である飯尾醸造に入社。2012年に当主に就任してからは、経営理念を「モテるお酢屋。」と定め、多様なステークホルダーとの共存共栄をめざして、独創的な経営企画を次々と実践している。全国の顧客を招いた田植え・稲刈り体験会の開催や、「美食」で地元に人を呼ぶ仕組みづくり、日本の食文化継承プロジェクトなど、お酢屋の垣根を超えて活躍中。

井上大輔
エンビジョン代表取締役
2017年、前身となるクリエイティブプロダクションの代表取締役就任、翌年MBOし独立。クリエイティブが担う領域でポジティブな未来を実現させるべくenvisionのパーパス、ナラティブをリードする。envisionと同様のパーパスを掲げる企業・個人が増えることで、社会が、日本が前進すると考えている。

藤巻功
エンビジョンCOO兼CBO
事業成長を加速させ、人を動かす「クリエイティブのチカラ」を信じているブランディングの専門家。国内大手広告代理店等を経て、インターブランドジャパンにて戦略ディレクターとして、グローバルを含む多様な業界の大規模プロジェクトを多数リード。その後、楽天グループ、KPMGコンサルティングにてブランディング/マーケティング&クリエイティブを統括。envisionでは、社会課題を解決するWoWなブランド・クリエイティブ開発、ブランディングの民主化に邁進する。
Contents
「丹後を世界に誇れる美食の町にする」、そう決心した理由。
藤巻
近年は「丹後を日本のサンセバスチャン(スペイン・バスク地方にある美食の町)に」をスローガンに掲げて、地域の魅力を高める取り組みをされていますが、これにはどんなきっかけがあったんですか?
飯尾氏
そのスローガンをつくったのは、私が初めてバスク地方を訪れた2015年のことです。あんなふうに町全体が魅力的になれば、飯尾醸造の未来にもメリットがあると思ったんです。ただ正直に言うと、本当にお手本にしたかったのはサンセバスチャン近くの漁村ゲタリアというところ。そこには予約の取れない超人気レストランが火付け役になって、魚の炭火焼きが町のコンテンツになっているんですね。それを見た時、町の規模から言っても同じようなことが宮津でもできると思いました。

飯尾氏
ただ当時ゲタリアなんて言っても誰も知りませんから、ようやく食通の間でパワーワードになり始めていた「サンセバスチャン」をスローガンに使ったわけなんです。
藤巻
海外での刺激が、新たなアイディアの源泉だったのですね。そういうメディアに注目されるようなキャッチーさの匙加減も絶妙だと思います。そこからレストラン「アチェート」の経営につながっていくわけですか?

飯尾氏
はい。アチェートの入っている古い商家は、私の地元の先輩が何年も保存活動を続けていた建物でした。そんな中で「入居するテナントを4軒確保してくれるなら」という条件付きで、ようやく買主が見つかったんですが、入居者が決まらず先輩が困り果てているのを見ていました。そんな中でバスク地方を旅して「美食で町を盛り上げたい」と考えた時、浮かんだのは「あの商家をうちが買い取ってレストランをやろう」ということでした。
藤巻
でもお酢屋さんがレストランを始めるのは並大抵のことではないですよね。
飯尾氏
はい。当然、両親は大反対でした。さらに普通なら補助金を使うところでしょうが、行政から一銭も貰わずにやってこそカッコいいし、自分の覚悟を示すことにもなると考えたんですね。結局1億円かかり、借金も抱えました。
井上
地域が盛り上がることで市場が育ち、飯尾醸造も伸びると考えて投資したんですね。
飯尾氏
2018年に始めた「世界シャリサミット」もその一環です。先ほどゲタリアのお話をしましたが、ゲタリアが魚の炭火焼きで世界一になっている姿が「シャリサミット」のヒントになったんです。これは「鮨サミット」ではないところがミソで、丹後のようなマイナーな土地は、魚がおいしいだけでは他地域に勝てません。でもシャリなら酢や米、食品化学に通じている飯尾醸造の価値が発揮でき、競争から離れられます。

藤巻
そうですよね、鮨ではなく、シャリにフォーカス、というのがユニークですし、一流の職人を宮津に呼び込み、食のプロの間で宮津の地位を上げていく仕掛けが秀逸だなと感じます。
放っておくと消えてしまう「本物」を100年先まで残していくために。
藤巻
地元だけでなく、他の地域の方々ともネットワークをつくって活動しておられますね。
飯尾氏
はい。2016年に、日本の伝統的な食文化の伝承を考える「HANDRED(ハンドレッド)」というユニットを立ち上げました。酒、醤油、酢、みりん、かまぼこ、お茶といった食品のつくり手6社からなるユニットで、手づくりを意味する「HAND」に、絶滅危惧種をあらわす「RED」を掛け合わせ、それらを100年先(HUNDRED)の世代まで残していきたいという願いを込めたネーミングなんです。
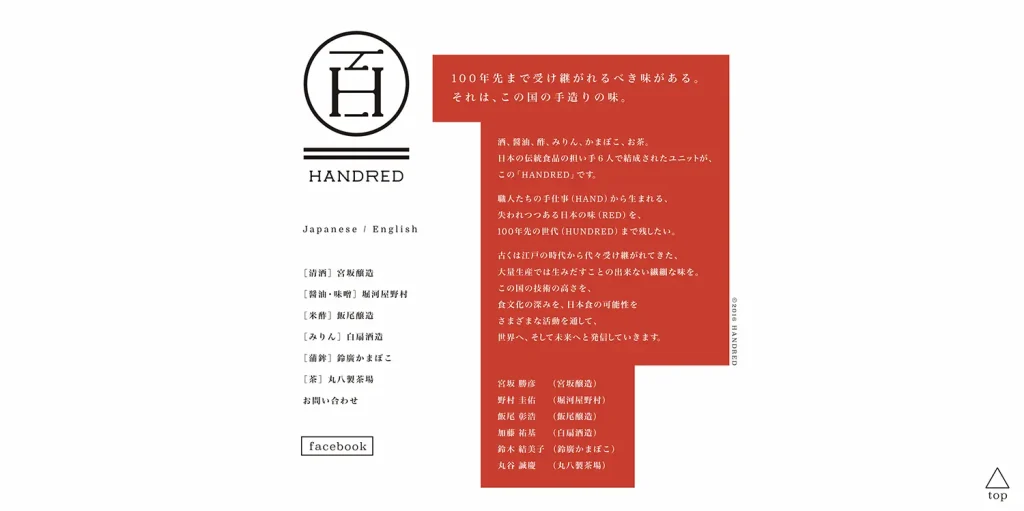
藤巻
大量生産では生み出すことのできない繊細な味を大切にされているところばかりですね。
飯尾氏
いい材料を使った本物のものづくりには、機械化されたものづくりにはない尊さや、「応援したくなる」おいしさがあります。それを守ることは日本の食文化を守ることにつながると思っています。
井上
たとえ非効率でもトラディショナルなやり方でいいものをつくっている自負がおありなんですね。
飯尾氏
うちは売上や規模を拡大していこうとは考えていなくて、生産量でいうとピークだった30年前からは10%ほど減っているんです。その代わり、よりクオリティの高いものをつくって単価を上げてきました。ネットによる自社直販もいち早く2000年からやってきたので、利益率は上がっています。
藤巻
まさに「競わずして生き残る」という哲学を地で行かれていて、そういった姿勢は他の地域ブランドにも参考になる点が多そうです。他の地域ブランドとの連携としては、他にどんな事例がありますか?
飯尾氏
最近でいうと、自転車屋さん、ワイナリー、焼酎製造元などの地域ブランドなどに対して、経営理念の言語化からブランド戦略づくり、マーケティングまでお手伝いしています。こんなふうに各地の異業種ブランドとつながるようになったのは、キリンさんが2016年に立ち上げられた「地域創生トレーニングセンタープロジェクト」という事業に、プロデューサーとして参加したことがきっかけです。そこでは参加者同士でお互いの町を見せ合う取り組みがあって、うちがホストになった回は、全国から集まった40名ほどのメンバーに、2泊3日で丹後の地場産業をフィールドワークしてもらいました。
藤巻
自社でのお取り組みや知見をコンサルティングに活用されているのですね。中川政七商店さんを思い出しました。
飯尾氏
キリンさんのスポンサードが終わった後も、メンバー10名で出資しあって「インターローカルパートナーズ」という会社をつくり、活動を継続しています。

藤巻
つなぐという役割がうねりとなって広がっていますね。
従業員を大切に、ブレない活動を続けていけば、世界がちゃんと見つけてくれる。
藤巻
この先に、どんな未来像を描かれていますか。
飯尾氏
今後はスタッフの待遇をより高めていきたいと思っています。年収を上げることに加えて、2028年度中に社員食堂をスタートさせることを、2023年の経営計画に盛り込みました。モットーは「日本で一番原価の高い社員食堂」で、有機野菜や平飼いの卵など、できる限りつくり手の顔が見える食材を使うつもりです。その実現に向けて、今年6月からまずはテストで1日10~15人分のランチを無料提供しているんです。

飯尾氏
これは、社内みんなの食のリテラシー底上げのためでもあります。飯尾醸造に働きに来てくれる人のうち、もともと食への関心が高い人はどちらかというと少数派で、「たまたま職場が近かったから」とか「希望する条件に合っていたから」という理由が大半です。でも本来、私たちの食のリテラシーは、お客様以上に高くあるべきですから、そこは日々同じ釜の飯を食う中で、自然に体で理解してもらうのがいいと思うんです。「同じ豚肉でも、肥育日数と餌が違えばこんなに味わいが違うものなのか」とかね。
藤巻
食を切り口にした新しい地域企業のモデルになりそうですね。社員食堂のレシピ本の出版も、勝手に楽しみにしています(笑)。ちなみに海外へのアプローチはどのように考えられていますか?
飯尾氏
とくに海外向けに営業を強化してはいません。逆に公式サイトから英語表記を外したぐらいなんですが、機械翻訳を使って向こうが見つけてくれるので、今でも毎月のようにいろんな国から商談に来られています。毎年アメリカの料理学校の研修の受け入れ先にもなっているんですよ。おかげで、17〜18年かけて熟成させるプロ用の「赤酢」は、国内外合わせて150店ほどの江戸前鮨店に納入しています。もうこれ以上生産量を増やせないので、すでにウェイティングリストはいっぱいで、長ければ3〜4年待ちという状態です。

藤巻
そういった高級店ではブランドチェンジはほとんど起きないですからね。改めて、ビジョナリーな経営をされてきたことが今につながっているのだと実感しました。後篇では経営者対談として、普段はあまり語られないことも深掘りして伺ってみたいので、よろしくお願いします。
◼︎後篇につづく