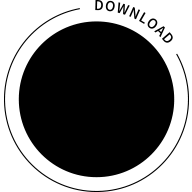INSIGHTS
2025/04/07
小さな企業にこそ、強いブランドを。ブランディング請負人たちの頭の中。【前篇】
対談記事

あらゆる業界で「ブランディング」という言葉が飛び交うようになった現代。しかし本当の意味での「ブランディングの民主化」は、まだ道半ばであると私たちは考えています。そこで私たちは、東京で活躍する二人のクリエイティブディレクターをゲストにお招きし、中堅〜中小企業のブランディングや、その課題についてクロストークを繰り広げることに。当社COO兼CBOの藤巻功が在籍していたインターブランドジャパンのOB仲間であり、独立起業してから10数年という小林建二郎様(ツバメヤ株式会社)と、今田佳司様(株式会社チビコ)。それぞれのスタンスから発せられる言葉に、耳を傾けてみましょう。
◼︎後篇はこちら

小林建二郎 様
ツバメヤ株式会社 代表取締役
京都工芸繊維大学 工芸科学研究科 博士前期課程を修了したのち、株式会社GK京都、インターブランドジャパンを経て、2007年起業。CI/VI開発をはじめ、パッケージ、広告、ウェブ、サイン計画のデザインワークや、ブランド戦略立案などを幅広く手掛ける。
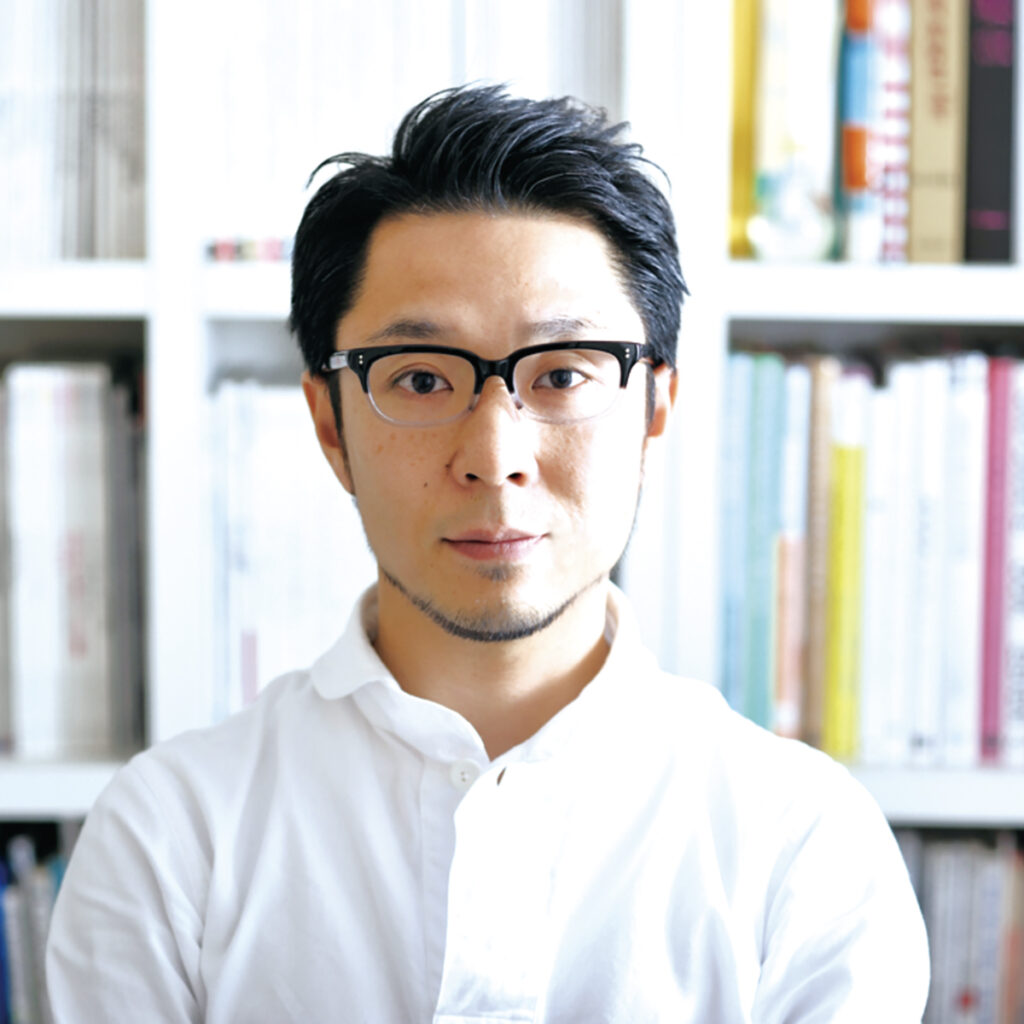
今田佳司 様
株式会社チビコ 代表取締役
大阪芸術大学卒業後、プロダクトデザイナーとして自転車の設計に携わったのちに、ブランディングを志向し方向転換。複数企業で経験を積み、2009年に起業。「ブランディングの川上から川下まで」をテーマに、ブランディング戦略の策定から各種デザイン制作まで手掛ける。

井上大輔
エンビジョン 代表取締役
2017年、前身となるクリエイティブプロダクションの代表取締役就任、翌年MBOし独立。クリエイティブが担う領域でポジティブな未来を実現させるべくenvisionのパーパス、ナラティブをリードする。envisionと同様のパーパスを掲げる企業・個人が増えることで、社会が、日本が前進すると考えている。

藤巻功
エンビジョン COO兼CBO
事業成長を加速させ、人を動かす「クリエイティブのチカラ」を信じているブランディングの専門家。国内大手広告代理店等を経て、インターブランドジャパンにて戦略ディレクターとして、グローバルを含む多様な業界の大規模プロジェクトを多数リード。その後、楽天グループ、KPMGコンサルティングにてブランディング/マーケティング&クリエイティブを統括。envisionでは、社会課題を解決するWoWなブランド・クリエイティブ開発、ブランディングの民主化に邁進する。
Contents
大手ブランドコンサルティング会社から独立10数年。
企業の課題と向き合う中で、今見えている景色とは。
藤巻
お二人は似た時期に起業されてますが、昔から独立を考えていたんですか?
小林氏
そこまで強く意識していたわけではなかったですが、一種の憧れというか「個としての自分」を強くしていった先にある分かりやすい姿として、独立起業をイメージしていたのは事実です。それに自分の好みとして、大きい会社に所属して大きい仕事をやる、ということにはさほど重きを置いていなくて、自分が納得した上で関われるかどうかの方が大事だと思っていたんですよね。GK京都にいた頃は、広告だろうがパッケージだろうが領域横断でいろいろやっていたのが、東京に来てみたら、組織的に分業化された世界。それが、ちょっともどかしい部分もあったんです。たとえば、僕が所属していたチームはパッケージの仕事が多かったのですが、他でやってるデザイン以外のことについては、思うことがあってもなかなか口出しするわけにもいかなかったりして(笑)。

今田氏
僕の場合、プロダクトデザイン出身なのでキャリア的には少し異質かもしれません。ただ、まだ「ブランディング」という言葉もなかった20代の頃から漠然と、ブランディング的なことをやりたいと思ってはいました。ですからそこから先は逆算人生。とにかく全てを吸収してやろうと考えて、プロダクトの設計に始まり、商品開発、広告、WEB制作と、必要と思われることは片っ端から経験しました。そうやって渡り歩いた末にインターブランドジャパンに移って、ようやくスキルセットが揃ったんです。今は、ブランド基盤づくりに必要なMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)策定やコミュニケーション戦略全般、それからVI含めあらゆるデザインに携わっています。
小林氏
うちはどっちかというと、株式会社チビコさんよりデザイン企画・制作寄りかもしれません。パッケージの仕事が比較的多いですが、時には商品企画やネーミング開発に関わることもあれば、ストーリーづくりだけで終わる仕事もあり、クライアントのニーズにカメレオン的に応えている感じですね。
今田氏
独立後の2年間は、とにかく実績をつくるのに必死で、どんな仕事でも断らずに受けていました。でも3年目以降は「元請けしかやらない・コンペは受けない」という方針でやってきました。デザイン会社ならそこまで考える必要はなかったかもしれませんが、ブランディング会社を標榜する以上、「何をやるか」はすごく考えてきましたね。ただ、11期目に当たる2020年は、1年まるまる仕事を休んだんですよ。それは前から決めてたことです。起業して7〜8年ぐらい経つ頃から、「このままでは次の10年を走れない」と思っていたので、9年目10年目は寝る間もないぐらい働いて、11年目はインプットと発信に集中しよう、って。それまではお客様のブランディングに必死で、自分のブランディングが後回しになってたんですよ。でもやっぱり、自分のブランディングができてない会社に、仕事を頼もうとは思いませんよね。
小林氏
バイオリズム的にも、そういう立ち止まるべきタイミングがあるんだってことを先に読んで、自覚的にやれたのはすごいと思う。自分も会社を始めて10年ぐらいの時かな、あらゆることに「飽き」に近い感覚になったと言ってもいいような時期があったんですよ。なんなら生活全般に対してすら(笑)。
今田氏
休んでいた間は、これからの自分の生き方、働き方含め、本当にいろんなことを考えたし、たくさんのインプットをしました。僕の課題意識として、うちにブランディング相談に来られる中小企業の社長さんと対等に話せるだけの、経営やファイナンスの知識が足りないという自覚があったんです。この先、「こういう業界にアプローチしたい」という自分なりの欲もあったので、やるべきこと・学ぶべきことは明確でした。

藤巻
中小企業の社長と対峙するには、やはり経営目線でお話できることがマストですね。
小林氏
そうやって基盤をつくれば、逆に堂々と「知らない」と言えることが増えそうですよね。わかってない時ほど変に知ったかぶりしてしまいがちだけど……。僕の場合、「飽き」の時期を乗り越えられた転機って、「人の役に立てることのありがたさ」に気づけたことなんです。世の中に数ある仕事の中で、僕にはデザインが向いていたのか、とにかく結果的にこの仕事をしているけど、もし歌が得意でそれが誰かの役に立つのなら歌を歌う人になってもいい。そう考えると楽になったし、今は日々前向きですよ。
ブランディングも、突き詰めれば人と人。
目指す未来に向かって、どこまで熱量を共有できるか。
藤巻
今って、仕事の依頼はどのように舞い込んできているんですか?
今田氏
今は集客の8割が直接の問い合わせです。今、うちのWEBサイトにはブログ記事が100本ぐらいあって、「ブランディング」とか「デザイン」というキーワードで検索上位に上がっているんです。そういったブログを読み込んだ上で来社される方が多く、受注率は結構高いです。ただ、ブランディングって1プロジェクト2〜3年ぐらいかかる世界なので、もしお互いに「ちょっと違うな」と思ったら、仕事が始まる前にやめておく方がいい。そんな話をわりと最初の段階でするようにしています。
藤巻
会社と個人のバランスは難しいですが「結局その人とやりたいか」ってことですよね。

小林氏
うちも、長くつながってるクライアントとは人間的な共感があります。自分はわりとそういうウェットな部分を大切にしているし、なるべく熱量のある人と一緒に仕事をしたい。中小企業の社長さんにはそういう方が多いですよね。一方で、国や自治体の補助金で行われてる地域活性化事業なんかは、関わる人も多く、メンバー間での温度差が大きいことがある。その中に必ずいらっしゃる「熱量の高い本気の人」にはこっちも熱意を持ってぶつかるし、なんとかお役に立ちたいと思って頑張るのですが、悲しいかな「これから」という時に年度区切りで終わりが来ちゃったりするんですよ。
藤巻
地方を考える時、そこは避けて通れないですよね。もちろん中には、その土地の名士の二代目三代目なんかが危機感を持って動いて、地域を活性化してるケースもあります。ただ資金力がないと、それも難しいんですよね。
ブランディングという長い道のり。
その始まりに、膝を突き合わせて共有すべきことは。
今田氏
助成金や補助金を使って、何かをデザインして「地域活性化をやったつもり」になっているケースが多いのは、そもそもブランディングというものに対する理解が、表層的なものに留まっているからでしょうね。うちにご相談に見える中小企業さんでも、「その期間と費用では、さすがに難しいのでは」というケースはままあります。
井上
設備投資なら融資も受けられるし、わかりやすいんですけど、ブランディングの価値って無形なだけに、理解されづらいですよね。だから単にロゴや名刺、ウェブサイトをデザインするだけのことで「100万円でブランディングします!」みたいなアピールしている会社に引っ張られてしまう。でもそうした施策は本質的なブランディングとは少し違うと思うんですよね。

今田氏
うちに問い合わせに来られる方々を見ていても、ブランディングに対する理解のレベルって本当にバラバラです。ロゴや名刺をつくる、いわゆるCIがブランディングだと思っている方がいる一方で、インターナルブランディングまで視野に入れた、リテラシーの高い会話からスタートできるケースもあります。ですから、まず最初に「ブランディングをどう捉えていますか?」と聞きますね。
小林氏
今田さんのところはブランド戦略に軸足を置いているけど、うちは「ブランディングをやってます」じゃなくて、「ブランディングのためのデザインをやっています」と言います。主役は私たちじゃなくてあなたですよ、と。そうじゃないと嘘になりますから。
今田氏
そうですね。うちも「一緒に創るんだから大変ですよ」という話はします。ともに汗をかいてもらうし、さらけ出してもらわなくちゃいけないこともありますよ、と。デザイン会社に100万円払ってロゴと名刺とウェブサイトを新しくするだけでは、望む結果にはならないと思いますよ、ということもはっきり言いますね。
藤巻
ブランディングの定義と範囲は、最初に膝を突き合わせて意識合わせをしないといけないですね。財務の人と人事の人とでは求めるものが違うように、定義って、置かれている立場の数だけありますから。ブランディングの解釈はある程度広くてもいいんですが、本質はシンプルで、企業やプロダクト、サービスに内在しているものの「らしさ」や「譲れない本質」をきちんと整理・発掘して、未来に向けて磨いていきましょうっていう、それだけのことだと思うんです。加えて、心理的ハードルは下げたいですが、「ブランディングは、お手頃に1-2ヶ月でできる」と安易に考えられてもいけませんね。
今田氏
僕も、やっていて一番意味を感じるのは、「もったいない」と思う時です。すごい魅力があるのに、当事者が自社の強みに気づいていない、ということ。だからまずは己を見つめ直してみれば、やれることは山ほどあるし、そこからはもうジャンプあるのみです。

◼︎後篇につづく