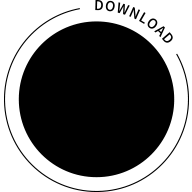INSIGHTS
2025/04/07
小さな企業にこそ、強いブランドを。ブランディング請負人たちの頭の中。【後篇】
対談記事

東京で活躍するクリエイティブディレクター二人をエンビジョンにお招きしてのCritical Creativeクロストーク。「ブランディング」に対する理解のレベルが、人によってバラバラであることのむずかしさを語り合った前篇に続き、後篇はいよいよ核心へ。ブランドが向かうべき「北極星」を見つける重要さから、クリエイターの活かし方、はたまた生き方・働き方の話まで、縦横無尽に広がったトークをお届けします。
◼︎前篇はこちら

小林建二郎 様
ツバメヤ株式会社 代表取締役
京都工芸繊維大学 工芸科学研究科 博士前期課程を修了したのち、株式会社GK京都、インターブランドジャパンを経て、2007年起業。CI/VI開発をはじめ、パッケージ、広告、ウェブ、サイン計画のデザインワークや、ブランド戦略立案などを幅広く手掛ける。
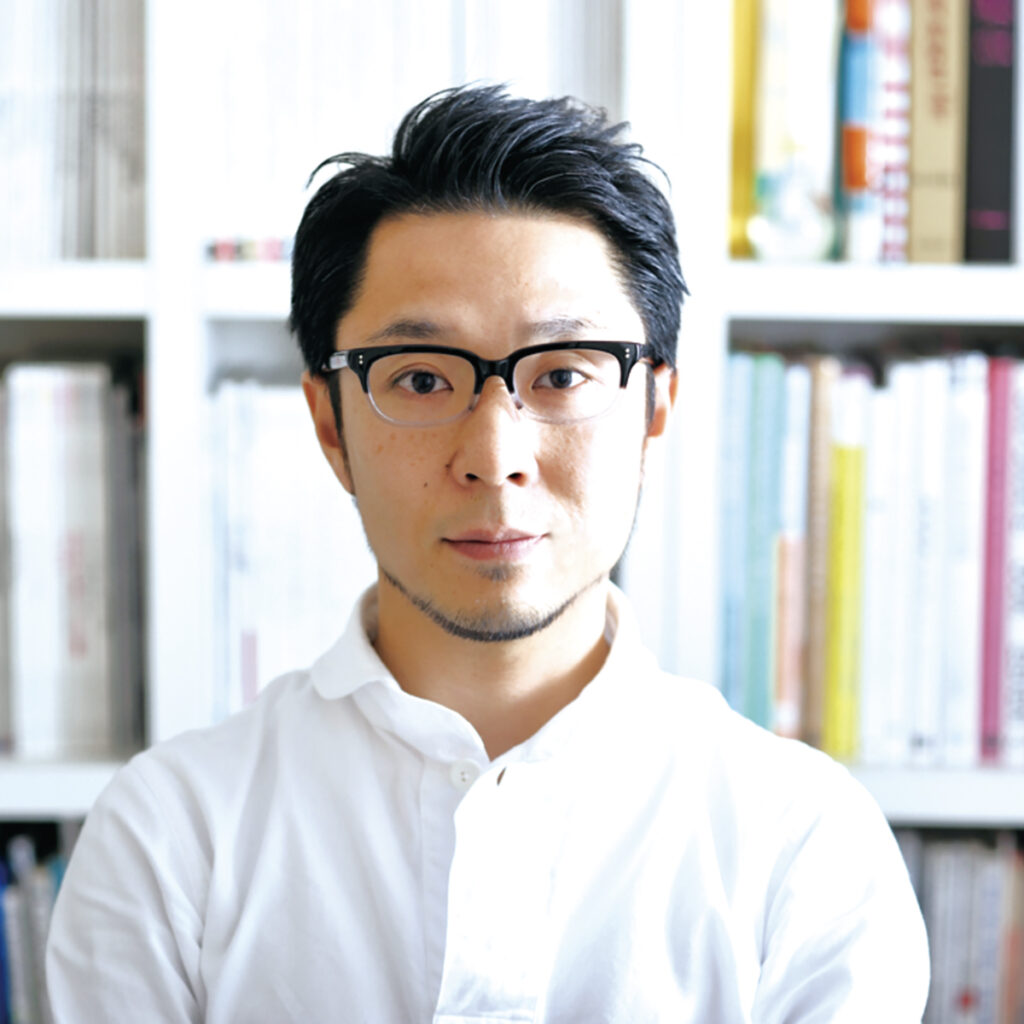
今田佳司 様
株式会社チビコ 代表取締役
大阪芸術大学卒業後、プロダクトデザイナーとして自転車の設計に携わったのちに、ブランディングを志向し方向転換。複数企業で経験を積み、2009年に起業。「ブランディングの川上から川下まで」をテーマに、ブランディング戦略の策定から各種デザイン制作まで手掛ける。

井上大輔
エンビジョン 代表取締役
2017年、前身となるクリエイティブプロダクションの代表取締役就任、翌年MBOし独立。クリエイティブが担う領域でポジティブな未来を実現させるべくenvisionのパーパス、ナラティブをリードする。envisionと同様のパーパスを掲げる企業・個人が増えることで、社会が、日本が前進すると考えている。

藤巻功
エンビジョン COO兼CBO
事業成長を加速させ、人を動かす「クリエイティブのチカラ」を信じているブランディングの専門家。国内大手広告代理店等を経て、インターブランドジャパンにて戦略ディレクターとして、グローバルを含む多様な業界の大規模プロジェクトを多数リード。その後、楽天グループ、KPMGコンサルティングにてブランディング/マーケティング&クリエイティブを統括。envisionでは、社会課題を解決するWoWなブランド・クリエイティブ開発、ブランディングの民主化に邁進する。
Contents
そのブランドが向かうべき北極星は、どこにある?
藤巻
ブランディングのはじめの第一歩は「自分たちがどこに向かいたいのか」という北極星をしっかり見定めることだと思います。そしてその北極星と現在地のギャップを、適切なブランディングで埋めていくことですね。広告代理店的文化が幅をきかせていた時代は、テレビなどのマスメディアを駆使して露出を上げ、認知拡大につなげることがブランディングだと考えられていました。その一方でBtoB企業にブランディングは必要ない、という風潮もかつてはありましたよね。これもブランディングを経営戦略として正しく捉えていないことが要因かと。昨今のBtoBでは、グローバルでの成長、国内での採用強化、お客様の先のお客様目線での提言、このあたりが共通のブランディング・テーマですね。
井上
僕はBtoB企業のブランディングって、社長のためにあると思ってます。自社のブランディングの概念がしっかりしていれば経営の意思決定を迷わないし、よく言われる「経営者の孤独」も感じなくてよくなるんじゃないかと。

今田氏
その観点では、うちは顧客の9割がBtoB企業なんです。有形商材のビジネスだけでなく、人材派遣とかシステム開発など、無形商材のビジネスも多くて、モノありきのブランディングというより、企業ブランディングですね。特に、ビジネスモデル転換にまつわるリブランディングがほとんどです。小林さんのところはBtoCのメーカーさんが多いと思いますが、どうですか?
小林氏
これだけモノが世の中に出回って、本質的に新商品なんていらないことがほとんどのこの時代でも、メーカーは「じゃあもう新しいモノをつくるのやめます」というわけにはいかない。そんな状況でつくられた「新しいモノ」をどうやって買ってもらうのか?ひと昔前までは、「ブランド体験」と言って、そのモノが別世界に連れて行ってくれるかのようなイメージづくりがブランディングで大切とされる要素だったと思いますが、それだけではもう通用しないのが今です。むしろ今は、どんな人がどんな思いで、どうやってモノやサービスをカタチにしているのかという「プロセス」が意味を持つんだと思うんです。生活者はそのプロセスに意義を見出し、その理念や姿勢に一票を投じるようにお金を払ってる。そこでの信頼を保証するものとして、ブランドが機能してるのかなと。
藤巻
コンサルティング会社の経験で分かったことは、サイエンス思考のスマートな頭脳を持っている人はたくさんいること、そしておよそ同じロジックと答えを持っていることでした。これは、大きな気づきでした。徹底的に数字やロジックを駆使することで、何らかの差異を見出そうとする。しかし、精緻なマーケティングリサーチをすればするほど、結局、同じ結論が出てくるわけです。ごく一部のすごいプロダクトアウトを除けば、大抵のものは機能だけではなかなか差別化が難しい時代になりましたよね。そこではチャーミングで、「なるほど」という視点でストーリーを語って人をワクワクさせる「意味性」が大切です。
今田氏
最近、やたらデザインの味付けが濃くなっているのはどう思います?売り場で一瞬で認知されるわかりやすさ、強さが求められているというか。そういったデザインが短いスパンでリニューアルを繰り返しながら、世に溢れているのが気になるんですよ。ブランドってこんなに短命でいいの?って。かと思うと、ハイブランドのロゴが「フォントで打ったのかな?」というようなものにどんどん変わっている。機能的で効率はいいかもしれないけど、没個性だと思いませんか?

藤巻
デザインがフラットになっているのは、デジタル化の影響もあるでしょうね。デバイスで表示されることを考えて合わせざるを得ないという。一方で店舗でのタッチポイントは味付け濃いめになっているというのは面白い指摘ですね。
小林氏
個人的には、マスを狙うきれいなデザインはもういいから、これからは、どれだけニッチで偏愛性の強いものをやれるかだと思っています。ほどよく器用にまとまった既視感のあるものじゃなく、いい意味で「気持ち悪い」ものっていうか。
藤巻
特定の少数に深く刺さるというね。バズを狙ってやるのではなくて、大事なのは、潜在的な問題意識を正しく刺してアウトプットしたらこうなった、ということですよね。
クリエイターが力を発揮するために必要なのは、
クライアントの信念や矜持。
今田氏
いいものを作れば売れていた時代は終わり、今は誰から買うかが問われる時代です。社長自ら旗振り役になってオウンドメディアで発信をしている企業が増えているのもそういう流れからですよね。
小林氏
ただ、そこで社員が置き去りになって「他人事化」が進んでしまってはいけないと思うんです。「どこへ向かいたいのか」っていう意志が、社内に浸透してこそのブランディングじゃないかな。
藤巻
時代性・将来性・成長性を加味したブレのない軸による「コーポレートブランディングによる全社変革運動」の推進が肝かと思います。社員にとっては働きがいある魅力溢れる求心力として、顧客や市場にとっては価値を体感できる遠心力として作用させていく、そんなつながりですね。最近のクライアント側の特徴や変化で、何か気になる点はありますか?
今田氏
クライアントは中小が3割というところですが、最近気になるのは、企業規模が大きくなるほど、担当者が決定権を持っていなくて、モチベーションが上がりきらないということ。ブランディング専任じゃなくて、本来の部署との兼務なのも辛そうで。
小林氏
かといって、タスクフォースみたいに短期的なチームをつくれば解決するとも限らない。モチベーションが低いということに加え、ブランディングに取り組む企業側の発注スキルが下がっているように感じることが増えています。たとえばパッケージでいうと、以前はひとつの製品への思い入れが強いと同時に、印刷などの専門知識もデザイナー並みに詳しくて、だからこそ明確な目的に沿った的確な発注ができる社員さんがクライアントにいたものです。ただ、そういう知識や姿勢が社内で継承されていないのか、全部外部に丸投げして、出てきたものを見てようやくちゃんと考え始める、みたいになってしまっている。それは仕事の楽しさを自ら手放してしまってることとイコールじゃないかな。
藤巻
そこは生産性至上主義とか働き方改革の影響もあるでしょうね。私はどっちかというと、クリエイティブとかデザインに対する経験とか知識はなくてもかまわないから、少なくとも自分たちがどうなりたいかという信念や矜持は持っていてほしい。作業は外部化したとしても、「考える」ことまで手放してはいけないと思うんです。そこはAIではなく人間のやるべきことだから……。

今田氏
カッコよくしてください、おしゃれにしてください、だけで来られても困りますよね。どんな仕事だって、どうせやるなら楽しむ努力をすべきで、そのためには、先方が何でも話せる空気をつくることも、われわれの役割だと思う。実際、大手コンサル会社に依頼したら、圧が強くて物申せない雰囲気だったって話も聞きますから。
小林氏
われわれって、設定したゴールまで一緒に走る時間を、楽しいものにする責務を負ったサービス業でもありますよね。そこでAIにはない「人間らしさ」をどれだけ発揮できるかが問われているんだと思います。楽しみあってつくるっていうことは人間にしかできないことだし、人生も仕事も、与えられた時間をいかに面白がれるかですね。
井上
AIが発展していく中で、ブルシット・ジョブは機械に任せて、自分たちはもっと人間らしく泥臭い情熱とか志とかの本質を追求していきたいですね。
「ブランディングの民主化」は、未だ道半ば。
今田氏
エンビジョンさんが掲げている「ブランディングの民主化」についてですが、僕はそれ、もう達成されていると思っていて、今はその次の「民営化」のフェーズだと思います。つまり大小問わずいろんな会社が、レベルの差こそあれブランディングらしきものができるようになったと。そこで次に求められているのは「大衆化」。誰もが困った時にすぐブランディングの相談ができるような距離感にまでは、まだなっていないですよね。そこはどうお考えなのか聞きたいです。
藤巻
僕たちが考えてる「民主化」は、ブランディングを手がけるプロフェッショナルが増えるという意味ではなくて、受け手側、クライアント側の問題なんですよ。そもそも「持続可能な経営のためにブランディングが必要だ」と考えている企業が、まだまだ相対的に少ないですから。
今田氏
でもそこの意識も間違いなく上がっているというのが、うちに相談に来られる企業さんを見ていての肌感ですけどね。中小の社長の意識がここまで上がってるのか、と思うことは多いですよ。
小林氏
それは、今田さんのブログを読んだ上で、理解度のある人が来られてるからじゃないかな。確かにひと昔前と比べれば、一見クリエイティブと無縁そうな人がブランディングを語るケースは増えました。ただそれは単語として知ってる程度のことで、ブランディングの本当の価値とか、クリエイターの活かし方の認識は、まだズレてると思うんです。たとえば相変わらずデザイナーは「絵が上手な人」ぐらいに思われている節があって、仕組みや戦略的なことは、デザイナーが関わる領域だと思われていないから、オリエンテーションの初動からズレてしまうんです。核心に踏み込んだ情報を開示しきれてないから、後々になって「その話、もっと早く教えてほしかったです!」ということがよくありますね。

クリエイターとは、クライアントが
自社の価値を再発見するための触媒。
今田氏
これからは、昔ならやらなかったような領域のことも頼まれるようになっていきますよね。MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を定めるところから、SNSマーケティングや生成AIの活用まで、知識や対応力の広さと深さが、同時に求められるようになっていくでしょうね。
藤巻
私たちは、そこはオーケストラ型で、クライアントの経営課題を確認しニーズを読みながらプロジェクト毎に最適な外部専門家をアサインしていきたいと思っています。
今田氏
どうしても目に見える費用対効果や即効性を求められがちですが、ブランディングって、内在化してる価値を掘り起こして磨き上げる、長期的な取り組みです。なのにブランディングの話をしている時に、「今、何が流行ってますか?」と聞かれちゃうんですよね。そんな時は「ブランディングとマーケティングは違うでしょう?」という話をします。
藤巻
そこはグローバリズムの弊害もあるかもしれませんね。「ステークホルダー資本主義」が注目を集めるきっかけとなったのは、2019年8月の米経済団体ビジネス・ラウンドテーブルの声明ですね。「米国の経済界は株主だけでなく、従業員や地域社会などすべてのステークホルダーに経済的利益をもたらす責任がある」とする声明が発表され、話題を呼びましたけど、日本にはもともと「三方よし」の哲学があり、こういったことはずっと昔から言ってるんですよね。これまではどうしても海外の先行事例ばかりを見て「だから日本は遅れている」という言説がまかり通っていましたが、これからは、海外動向は把握しつつも、日本固有の文化に根ざしたブランディング(らしさづくり)を、誇りを持って推進していく気概が必要なんじゃないかと思います。
小林氏
クライアントが自社を再発見するための触媒に、われわれがなるべきですよね。
藤巻
そこに辿り着くプロセスや仕組みを、Critical Creativeを通じてこちらがご提案していかなければならないと思っていますし、その道のりでお二人とも協働できればうれしいです。今日は本当にどうもありがとうございました。

小林様と今田様、スタンスの違いこそあれど、ブランディングを巡って飛び出す鋭い発言は、第一線で活躍してきたプロフェッショナルならでは。ブランディングとは単に見栄えを整えることではなく、長期的な経営戦略と経営システムとのセットで考えるべきものです。そのことに対する理解が、日本の9割以上を占める中小企業に広がり、クリエイティブの力を適切に活用できるようになれば、日本はもっと豊かに楽しくなるはず。そんな思いを新たにしたクロストークでした。