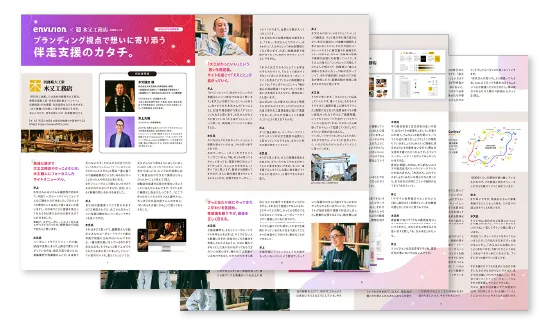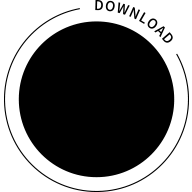INSIGHTS
2025/07/31
「ブランドマネジメント経験ゼロ」で挑んだ、SUBARUグローバルブランディングの勝因。【後篇】
対談記事
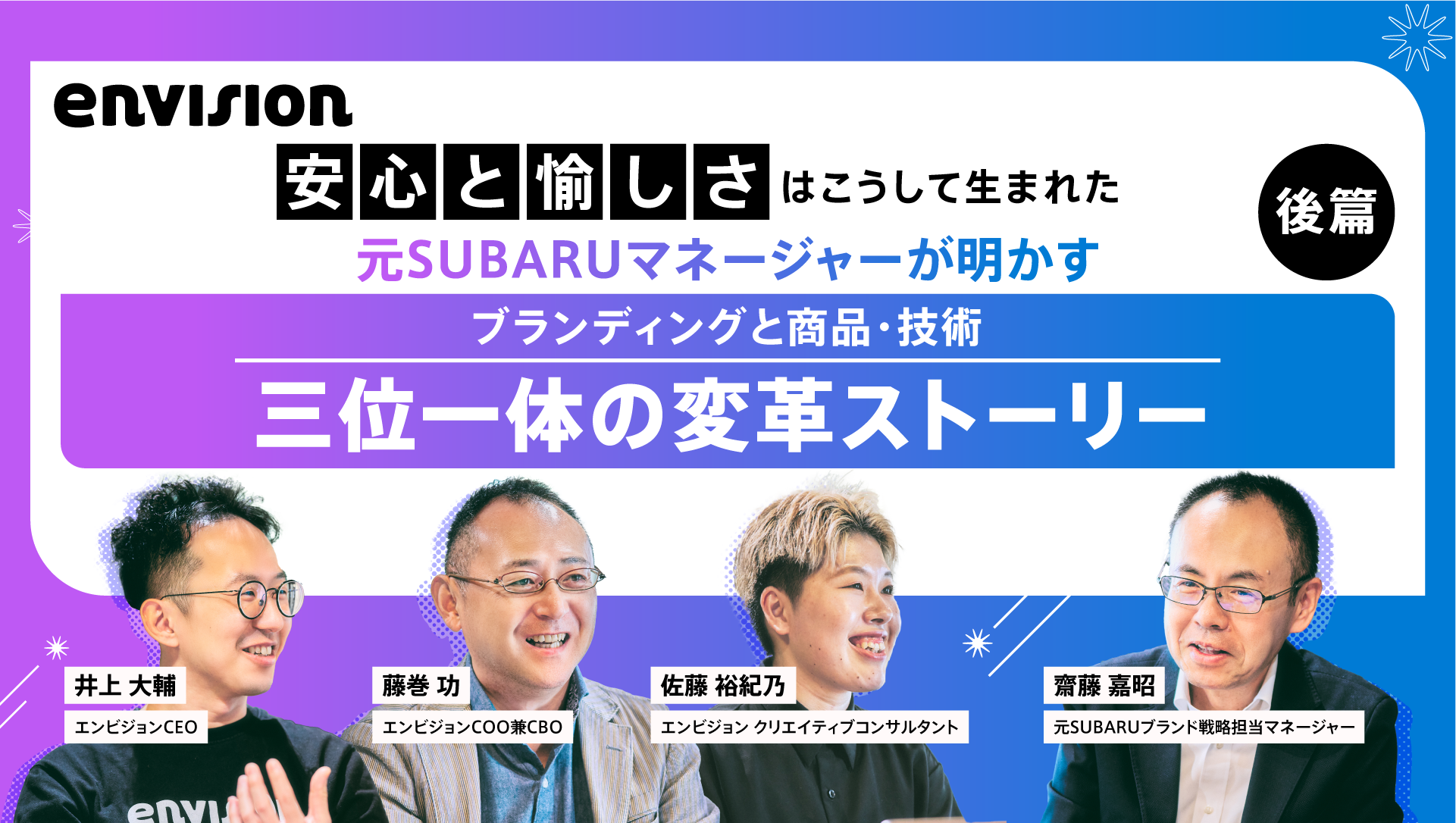
社長秘書から一転、「ブランドマネジメント経験ゼロ」の立場で、SUBARUのグローバルブランディングを推進してきた経験を持つ齋藤嘉昭様。前篇では、暗中模索の日々の末、自社の固有価値の言語化に貢献し、社内外に浸透させるまでのプロセスを追ってきました。後篇では、そのブランディングがもたらした効果について伺います。齋藤氏が自身の経験を活かしてまとめた「実践コーポレートブランディング〜悩めるブランドマネージャーを導く 10 か条〜」についてのご紹介もあり、必見です。
◼︎前篇はこちら

齋藤嘉昭 様
元SUBARUブランド戦略担当マネージャー
1987年に富士重工業株式会社に入社。米国ゼネラルモーターズ社との提携業務を経験したのち、社長秘書を経て、2007年に新設されたグローバルマーケティング本部へ。今なお使われている「安心と愉しさ」という固有の価値を可視化することに貢献し、ブランド戦略立案をリードする。その後、航空宇宙部門の海外営業、米国ダラス事務所長など数々の重要任務を担当し、現在は航空機の関連企業で総務人事を担当。

井上大輔
エンビジョン代表取締役
2017年、前身となるクリエイティブプロダクションの代表取締役就任、翌年MBOし独立。クリエイティブが担う領域でポジティブな未来を実現させるべくenvisionのパーパス、ナラティブをリードする。envisionと同様のパーパスを掲げる企業・個人が増えることで、社会が、日本が前進すると考えている。

藤巻功
エンビジョンCOO兼CBO
事業成長を加速させ、人を動かす「クリエイティブのチカラ」を信じているブランディングの専門家。国内大手広告代理店等を経て、インターブランドジャパンにて戦略ディレクターとして、グローバルを含む多様な業界の大規模プロジェクトを多数リード。その後、楽天グループ、KPMGコンサルティングにてブランディング/マーケティング&クリエイティブを統括。envisionでは、社会課題を解決するWoWなブランド・クリエイティブ開発、ブランディングの民主化に邁進する。

佐藤裕紀乃
エンビジョン クリエイティブコンサルタント
大阪府出身。大学ではコト・モノ・情報を通じたデザインによる課題解決法を学ぶ。社会を多角的に分析し、新しい発想で課題にアプローチすることで「未来を良くしたいという前向きな想いが共鳴しあう世界」を実現したいと考えている。4歳から現在まで剣道を習い続けている。趣味はラジオ収録で、いつでもどこでもラジオMC風の進行をこなす特技を持つ。
Contents
成長のダイナミズム。ブランディングと商品・技術が三位一体となった結果、営業利益率が大幅に伸長。
藤巻
経営と一体となったブランディングによって、どんな変化が起きたかお聞かせいただけますか?
齋藤氏
経営的に大躍進を果たしました。直接的にブランディングの効果というわけではありませんが、SUBARUにとって最大市場である北米向けに、主力車種であるアウトバックやレガシィの車体サイズを大きくしたことで、北米での販売台数が3倍以上に伸びたんです。
藤巻
軽自動車から撤退したことも大きな決断でしたね。そういったさまざまな施策が噛み合って、2016年3月期には、17.5%と脅威の利益率になりましたね。

齋藤氏
はい。そもそも軽自動車はSUBARUが自動車事業を始めたときからのいわば祖業でしたが、国内市場向けに特化したもので、世界的には通用せず、なおかつ軽自動車市場は競合大手がひしめく激戦区でした。軽自動車からの撤退は、吉永社長が決断をもって「選択と集中」を行ったもので、北米市場を経営の柱とすることと合わせて利益率の大幅アップにつながりました。
やはり重要なのは、ブランディングとものづくりの「言行一致」です。お客様に提供するブランド価値として「安心と愉しさ」を定めたのですが、ちょうど「EyeSight」というステレオカメラによる先進安全運転支援システムの市場投入と重ねることができたので、ブランドと商品も強く訴求できたと思います。
逆に、ブランドと実際の商売に齟齬があるとお客様にも見透かされてしまいますよね。
北米市場で伸びたことで、有力な現地販売店がSUBARUを扱ってくれるようになり、さらに好循環が生まれました。

異文化を横断するマクロ目線を持ち、一貫性を守る大切さ。
藤巻
まさに、ブランド起点での経営の意思決定なのですね。「独自の価値創造」で見事にトランスフォームを果たしたSUBARU。ほかに社内ではどんな変化がありましたか?
齋藤氏
かつては「ブランドなんてしょせん広告宣伝の言葉遊びで、ものづくりに関係ない」といった疑いの目線があったのが嘘のように、「SUBARUのブランドは……」という発言があちこちで飛び出すようになりました。たとえば車の開発現場でも、「これはSUBARUの『安心と愉しさ』と言えるのか?」という議論が展開されるようになったのは大きな変化です。
先ほど、ブランディング着手に当たって、北米とオーストラリアの現地販売部門の意見を聞いたという話をしましたが、振り返ってみれば、彼らが言っていたのも「インターナルブランディングなくしてブランディングなし」「一貫性が大事」という2点でした。最初聞いたときはまだ腑に落ちていなかったんですが、やってみると本当でしたね。
藤巻
経営層の皆さんも、腹落ち感、自分事化されているのですね。 “Confidence in Motion”の世界観に基づいてグローバルで展開したコミュニケーションに対して、各国からの反応はいかがでしたか?
齋藤氏
“Confidence in Motion”はどちらかというとメーカーとして長期的、包括的な経営視点に軸足を置いて設定した言葉ですが、一方で販売部門では当然ながら彼らが直接対峙するユーザー寄りの視点を求めます。また我々日本人は「欧米」とひと括りにしがちですが、ブランドを伝える言葉を選ぶときに難しいのは、誰でも知っていそうなシンプルな英単語であっても、英国と米国、カナダ、オーストラリアでは、それぞれに市場環境や文化、言語感覚が違い、受け止め方が異なることです。たとえば、我々がブランディングプロジェクトをやっていた当時から、米国市場では現地販売部門の主導によるユーザー目線の「LOVE」というキャンペーンが大成功していて、これは今も定着しています。ただ、それをグローバルで 展開できるかというと話は別で、国や文化によって「LOVE」という言葉の使われ方、ニュアンスが違いますし、主力市場で成功しているからといって単純に乗っかるわけにはいきませんでした。
ただし、「LOVE」という言葉そのものは使っていませんが、今では日本市場でもSUBARUは米国での「LOVE」キャンペーンと同じような社会貢献や顧客体験の活動が盛んになってきたので10年を経てようやくブランドとして足並みが揃ってきたという印象もあります。

日本のSUBARU本社は、メーカーとしてモノづくりの現場も含めて、地域や部門の違いを乗り超えたマクロな視点で、様々な経営情報を踏まえて10年後のあるべき姿を見据えた経営の軸としてのブランドを考えなければなりません。一方、世界各市場の販売部門は、現地の販売の責任もありますし、目の前の顧客を重点的に意識したマーケティング視点のブランドというもう少しミクロな目線で見ているのが大きく違うところです。グローバルヘッドクォーターとしては、そのミクロ目線に引っ張られず、あるべきポジションを明確にする役割を担っていると思います。
藤巻
それがグローバルヘッドクォーターに求められるマーケット全体を俯瞰する視座、そして経営の鍵を握っている責任と矜持ですよね。2011〜2015年度の中期経営計画Motion-Vを実行された結果、米国市場に主軸をおいた商品開発、運転支援システム「EyeSight」をはじめとする安全対策や高効率生産への取り組みが功を奏して、2013年度までにMotion-Vの主要目標を前倒しで達成されました。
齋藤氏
私がブランディングの担当から異動した後ですが、2014年に発表した新中期経営ビジョン「際立とう2020」では、自動車メーカーとしては小規模なSUBARUが持続的に成長していくために、2020年のありたい姿を、「大きくはないが強い特徴を持つ、質の高い企業」と定めました。
佐藤
その姿勢は、ブランディングにトラウマを抱えていた過去の姿とは明らかに違いますね。
2018年に発表された新中期経営ビジョン「STEP(2018-2025)」では、「2030年交通事故ゼロ」を目指すという方針が掲げられており、現在のSUBARUが軸とする「総合安全」という考え方につながっているように感じました。
◼︎SUBARU公式サイト|SUBARUの総合安全
https://www.subaru.jp/safety/

齋藤氏
ブランドを確立する前のSUBARUだったら、とてもそこまで言えなかったと思います。でも自分たちはそういうブランドなんだと決めた以上は、行動の軸はおのずと決まってきます。いい意味で自分たちを縛る効力を発揮してくれるんですね。
「愛はあるけど惚れてない」。
ブランディングの鍵は客観視するまなざしを失わないこと。
藤巻
2017年に100周年を迎え、富士重工業株式会社から株式会社SUBARUに社名変更されたことも大きなインパクトがありましたね。
齋藤氏
実は大昔にも、社名を変えようとしたことがありましたが、その時はまだSUBARUという名前のネームバリューが低くて、自動車以外の航空機や鉄道、バス、産業機器などSUBARUを直接には名乗らない事業も多く、時期尚早で取りやめになったんです。しかしSUBARUの売上が拡大し利益率も向上してブランド価値が上がった結果、今度はむしろ航空宇宙部門からも、SUBARUの方がお客様に通りがいいと賛成されました。自分たちの命運を、その名前に賭けてもいいんだという想いが生まれたんだと思います。
藤巻
2018年にインターブランドジャパンから発表された「Best Global Brands 2018」では、初めて世界のグローバルブランド100に選出されました。日本からランクインしたのはトヨタやソニー、任天堂など7社だけですから、すごいことだと思います。お話を伺っていて思ったんですが、齋藤さんがブランディングをやりきれた理由は3つあって「世界の市場を俯瞰できたこと」「経営観点で SUBARUを客観視できたこと」に加えて、「やっぱりSUBARUが好き」ということなのかなと……。
齋藤氏
そうですね。確かに好きなんですが、車のセールス経験はなく、エンジニアでもなく、職歴の半分は航空機の海外営業ですし、常に「外から目線」ではあったと思います。ただ、私はもともと乗り物好きなのでSUBARUの技術のことはきちんと理解したいし、国際ビジネスの経験からグローバルマーケティングをやる以上は、アメリカ・ヨーロッパにおけるモータリゼーションの歴史や文化的背景を理解したうえで進めたいという志向はありました。好きなんだけど盲目的に溺愛するんじゃなく、冷静さと批判的精神も忘れずに……「愛はあるけど惚れてない」という感じでしょうか。

佐藤
だからこそ10年先が考えられるんですね。
井上
その視点でまとめられたのが、「実践コーポレートブランディング〜悩めるブランドマネージャーを導く 10 か条〜」ですね。
◼︎『超実践!ブランドマネジメント入門』(上條憲二 著/2022年)分担執筆
「実践コーポレートブランディング 悩めるブランドマネージャーを導く10か条」(pp.406~411)
https://d21.co.jp/book/detail/978-4-7993-2826-2
齋藤氏
はい。世の中にはブランド戦略の教科書は多数ありますが、カタカナ用語が多く使われていることがあり、実際にブランディングを担当する立場からすると参考にしづらいという問題意識をずっと持っていました。この本の著者である愛知東邦大学の上條先生からの提案もあり、私の実体験から得られた教訓・知見を整理し、最短距離でコーポレートマネジメントを進める手助けにできないかと考えて普遍化を試みたものです。今日は時間の都合で10か条をきちんとご紹介できないのですが、そのなかで3つ紹介したいと思います。
今日お話ししたこととつながりますが、まずは、「第1条 青い鳥は社内にいる」でしょう。
ブランディング作業の過程で、自社のあるべき姿、ブランドの“らしさ”の根幹を求めるわけですが、結局その核心となる要素は社内にある、ブランドの青い鳥は身近にいるということです。自社の歴史、課題や強み弱みについて自分たちの言葉で率直に、徹底して議論することでブランディングの核心を見つける必要があります。
次に「第8条 世界を見よ」です。
今や発した言葉やイメージは、インターネットで地球の裏側まで瞬時に伝わり、自分たちの知らぬところで、いつ何が起きるか、どこに影響するかわかりません。どんなローカル企業でも、ブランディングはグローバルに考える必要があると思います。また世界でビジネスを展開する企業は特に、本社がしっかりしたロジックをもって全体を統制することがグローバルなブランディングにとって必須だと思います。
そして「第10条 ブランドは一日にしてならず」ですね。
ブランドは一過性の広告キャンペーンではなくて、経営と表裏一体、長期視点の戦略だと思います。10年先に完成する覚悟で取り組む必要があります。ブランドのスローガンができたら終わりではなく、そこからが始まりです。子育てや庭木の手入れと同じかもしれません。辛抱強く育てていく必要があります。
井上
私も拝読しましたが、企業規模も職種も問わず、あらゆるビジネスパーソンに読んでほしい内容だと思いました。最後になりますが、齋藤さんがこれからのSUBARUに望むことはなんですか?
齋藤氏
足元は世界各地で騒乱状態ですが、方向性としては環境も含め様々な配慮、やさしさが求められる時代だと思います。そこにSUBARUは一番ふさわしいブランドになってほしいと思っています。かつてブランディングプロジェクトを担当していたときに構想していたあるべき姿と変わりませんが、ラグジュアリーとか大衆車とかといったヒエラルキーの軸ではなく、自然環境と調和しながらも、個人の自由な活動を支えて人生の伴侶であるような商品やサービス、そのあり方を、世界に提示できるブランドであってほしいですね。
藤巻
これからの時代におけるSUBARUのあり方に、一ファンとして、ブランディングの専門家として、そして日本人として、ワクワク感と期待感が湧いてきますね。本日はどうもありがとうございました。